祭り半纏(別誂え)男気一本、祭り衣装は半纏から
| 祭り半纏1 | 祭り半纏2 |
 |
 |
|
価 格 \35,000 寸 法 身巾68×身丈100cm 生 地 綿帆布 |
価 格 \35,000 寸 法 身巾68×身丈100cm 生 地 綿シャークスキン |
| 祭り半纏3 | 祭り半纏4 |
 |
 |
|
価 格 \25,000 寸 法 身巾68×身丈75cm 生 地 綿帆布 |
価 格 \25,000 寸 法 身巾68×身丈75cm 生 地 綿シャークスキン |
| ねぶたハネト用浴衣・たすき・しごき・おこし・腰ひも、承ります。 | ||
 |
・・・ねぶた伝説・・・ 平安時代初期、坂田上田村麻呂が征夷大将軍としてこの地に遠征したとき、 灯篭や笛・太鼓を使って敵をおびきよせたのが「ねぶた」の起源と言われてきた。 少し前までは「ねぶた」の最優秀賞を「田村麻呂賞」と称してきたが、現在は 「ねぶた大賞」と呼び変えている。田村麻呂起源説に疑問が生じたようだ。 もうひとつの説は、初代津軽藩主の為信が、京都で田舎者扱いを受けたことに 腹を立て、巨大な提灯を作って市中を練り歩いたことに由来する。これが京の都で 「津軽の大提灯」と評判になり以後年中行事となった。この大提灯、文献には残って いるが、「ねぶた」の起源かは定かではない。 |
 |
印し半纏(別誂え)
| 印し半纏1 | 印し半纏2 |
 |
 |
|
価 格 \45,000 寸 法 身巾68×身丈85cm 生 地 綿帆布 |
価 格 \45,000 寸 法 身巾68×身丈85cm 生 地 綿帆布 |
| 印し半纏3 | 印し半纏4 |
 |
 |
|
価 格 \45,000 寸 法 身巾68×身丈85cm 生 地 綿帆布 |
価 格 \45,000 寸 法 身巾68×身丈85cm 生 地 綿帆布 |

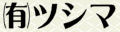
 半纏のご用命は
半纏のご用命は